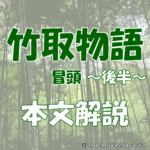みなさん、こんにちは、Keisukeです!
今回は竹取物語についてお話しします!
もくじ/Table of Contents
竹取物語について
ジャンルは、そのまんま、物語です。
作り物語、伝奇物語ともいわれます。
成立時期は、平安時代初期ということはわかっていますが、具体的に何年かまではわかっていません。
また、作者についても、貴族階級の男性ということまでは判明しており、候補者は何名かいますが、これまた具体的な人物は誰なのか不明です。
そして、この竹取物語は、日本最古のかな物語、日本で1番古い、ひらがなで書かれた物語といわれています。
それでは、いまだ多く謎も残る、かぐや姫のお話、竹取物語の最初、冒頭のおじいさんとかぐや姫の出会いの場面を、古文のままで読んでいきましょう!
この竹取物語 冒頭には、古文を楽しく読んでいくポイントが盛りだくさんなので、前半と後半の2回に分けて解説しますね!
竹取物語 冒頭 動画紹介
講義動画もありますので、よかったら活用してください!動画では前半&後半に分けず、一気に解説しています!!
本文解説(約25分)
復習&テスト直前確認用(約16分)
暗記テスト用(約30分)
竹取物語 冒頭 前半 本文解説
竹取物語原文
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。名をば、さぬきのみやつことなむいひける。
その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。あやしがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。それを見れば、三寸ばかりなる人、いとうつくしうてゐたり。
1文ずつ、順番に見ていきましょう!
1文目:今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
まずは、今は昔。
昔話でも、「むか~し、むかし。あるところに、おじいさんとおばあさんがいました」って始まりますよね。
この「むか~し、むかし」を、古文版にしたのが今は昔です。
ただ、古文の勉強では、今は昔の現代語訳は今ではもう昔のことだがと覚えてくださいね。
続けて、竹取の翁。
見慣れない漢字、翁の読み方はおきな、意味はおじいちゃんです。
竹取の翁で、読み方はたけとりのおきなです。
といふ者について説明する前に、歴史的仮名遣いと現代仮名遣いについて、説明します。
歴史的仮名遣いとは、今は昔、竹取の翁といふ者ありけりのような、古文特有の仮名遣いのことです。
これに対して、今、みんなが使っている仮名遣いを、現代仮名遣いといいます。
古文を読むには、現代語に訳すだけではなく、歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直す必要もあります。
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直すルールは、いくつかありますが、一気にすべてを覚える必要はありません。
竹取物語を読みながら、出てきたものを一つずつ、一緒に覚えていきましょう!
歴史的仮名遣いといふ者を現代仮名遣いに直すとき、注目してほしいのがいふです。
歴史的仮名遣いいふは1つの単語です。
そして、いふのふは、単語の2文字目、単語の最初にない『はひふへほ』の『ふ』です。
だから、歴史的仮名遣いの『ふ』は、現代仮名遣いに直すと『う』となり、歴史的仮名遣いといふ者を、現代仮名遣いに直すとという者です。
という者の現代語訳は、そのまんまという者です。笑
ありけりの現代語訳はいたです。
ですので、今は昔、竹取の翁といふ者ありけりを、現代仮名遣いに直すと 今は昔、竹取の翁(おきな)という者ありけりとなり、現代語に訳すと 今ではもう昔のことだが、竹取の翁(おきな)という者がいたとなります。
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
→今は昔、竹取の翁(おきな)という者ありけり。(現代仮名遣い)
→今ではもう昔のことだが、竹取の翁(おきな)という者がいた。(現代語訳)
続けて、2文目です!
2文目:野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。
野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。
野山は、そのまんま野山です。
まじりての現代語訳は分け入ってです。
テレビなどで、探検隊なんかがジャングルの中を進んでいくとき、草木をかき分けながら進んでいきますよね。
このかき分ける様子が分け入ってです。
竹を取りつつの現代語訳は竹を取ってはです。
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直すルールの2つ目です!
なので、歴史的仮名遣いよろづを、現代仮名遣いに直すとよろずです。
よろずの現代語訳ですが、みなさんはゲームなどで、"よろず屋"という言葉を聞いたことはありませんか?
この"よろず屋"では、武器、防具をはじめ、やくそうなどの道具、色々なもの、様々なものが売られています。
ですので、このよろづの現代語訳は色々な 様々なと覚えてください。
歴史的仮名遣い使ひけりを、現代仮名遣いに直すと使いけりです。
歴史的仮名遣い使ひは、1つの単語です。
そして、使ひのひは、単語の2文字目、単語の最初にない『はひふへほ』の『ひ』ですよね。
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直す1つ目のルールを思い出してください。
歴史的仮名遣い使ひの現代仮名遣いは使いで、使ひけりの現代語訳は使っていたです。
ですので、野山にまじりて竹を取りつつ、よろずのことに使ひけりを、現代仮名遣いに直すと 野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使いけりとなり、現代語に訳すと 野山に分け入って竹を取っては、色々なことに使っていたとなります。
野山にまじりて竹を取りつつ、よろずのことに使ひけり。
→野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使いけり。(現代仮名遣い)
→野山に分け入って竹を取っては、色々なことに使っていた。(現代語訳)
では、3文目!
3文目:名をば、さぬきのみやつことなむいひける。
名をば、さぬきのみやつことなむいひける。
名をばの現代語訳は名前をです。
さぬきのみやつこは、1文目に出てきた竹取の翁の名前です。
なので、さぬきのみやつこと竹取の翁は同一人物です。
なむは、助詞のなかでも係助詞というやつです。
とりあえず、「なむは係助詞なんや」と覚えてください。笑
助詞については、今は知らなくて大丈夫です。
『現代語の助詞』は中学校3年生で、『古文の助詞』は高校でたっぷり勉強しますので、安心してください!笑
ここで、係助詞なむについて説明します!
文字だけを見ると、「ん?ナニコレ??」となりますね。笑
これから、分かりやすく説明するので、安心してください。
では、下を見てください。
1. なむなしver.
名をば、さぬきのみやつこと いひけり。
2. なむありver.
名をば、さぬきのみやつことなむいひける。
係助詞『なむ』のない1. なむなしver.では、文末がけりとなっていますね。
このけりは、文の最後(終わり)にあるので、終止形という形です。
一方で、係助詞『なむ』のある2. なむありver.では、文の最後が終止形 けりではなくけるとなっています。
係助詞なむがあることで、文の最後(結び)が終止形 けりではなくけるになる、この現象を係り結びもしくは係り結びの法則といいます。
係り結びと係り結びの法則、両方を覚えて書けるようにしておいてくださいね。
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直すルールの3つ目!
今回のなむは、助詞のなかでも係助詞のなむです。
なので、歴史的仮名遣いなむは現代仮名遣いに直すと、なんと読みます。
この係助詞なむの働きは強意ですが、現代語に訳すときは 特に訳す必要はありません。笑
続けて、歴史的仮名遣いいひけるのひは、単語の最初にない『はひふへほ』の『ひ』なので、現代仮名遣いでは『い』に直し、いいけるとなり、現代語訳はいったです。
ですので、名をば、さぬきのみやつことなむいひけるを、現代仮名遣いに直すと 名をば、さぬきのみやつことなんいいけるとなり、現代語に訳すと 名前を、さぬきのみやつこといったとなります。
名をば、さぬきのみやつことなむいひける。
→名をば、さぬきのみやつことなんいいける。(現代仮名遣い)
→名前を、さぬきのみやつこといった。(現代語訳)
いやぁ~、ここまで読んでくれてありがとう!
ほんで、よく頑張りました!エライ!!
この竹取物語の冒頭には、みなさんが古文を楽しむために必要なポイントがたくさん詰まっています!
あまりに多くて、「古文イヤや~」という声も聞こえてきそうですが、大丈夫です!
新しく出てくる単語や文法や仮名遣いのルールに出会うたびに、一つずつ焦らず覚えていけばいいですよ!
ボクだって、古文をはじめて勉強したときは、何も知りませんでしたから!笑
下記のまとめの内容を理解できれば、今回の範囲はバッチリです!!
竹取物語 冒頭 前半 まとめ
文学史
現代仮名遣い&現代語訳
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
→今は昔、竹取の翁(おきな)という者ありけり。(現代仮名遣い)
→今ではもう昔のことだが、竹取の翁(おきな)という者がいた。(現代語訳)
野山にまじりて竹を取りつつ、よろずのことに使ひけり。
→野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使いけり。(現代仮名遣い)
→野山に分け入って竹を取っては、色々なことに使っていた。(現代語訳)
名をば、さぬきのみやつことなむいひける。
→名をば、さぬきのみやつことなんいいける。(現代仮名遣い)
→名前を、さぬきのみやつこといった。(現代語訳)
重要古文単語
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直すルール
係り結び(係り結びの法則)
ここまで読んでくれてありがとう!
以上、竹取物語 冒頭 前半でした!
後半も一緒に頑張ろう!!
書籍紹介
ここでは、ボクがこの記事や講義動画などを作成する際に使用した書籍を、指導者の方々向けに紹介します!
生徒のみなさんは、先生やボクの記事、動画の内容を理解してくれれば十分です!
竹取物語(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典/角川ソフィア文庫
1番オススメの書籍です!
"現代語訳→古文"の順で、一場面ごとに区切られ、竹取物語の全文が掲載されています。
コラムが豊富で、竹取物語に出てくるキーワードの理解が深まりまり、授業の小ネタも激増します!笑
現代語訳がとてもわかりやすいので、他は飛ばして、現代語訳を一気読みするだけで、竹取物語の全貌をイメージできます!
竹取物語の書籍はたくさんありますが、ボクはこの書籍の現代語訳が一番分かりやすかったです。
「竹取物語全体を、短時間で理解したい」という方や、「竹取物語を深く理解したい」という方の最初の1冊に最適です!
マドンナ古文単語230
言わずと知れた、大学受験生のバイブルです!笑
コチラの書籍、単語に対する解説が簡潔でわかりやすいです。
語源や単語の覚え方などにも言及しているので、授業での小ネタ集めに最適です!
大学受験用の書籍ですが、あやし、いとなど、竹取物語に出てくる単語はもちろん、枕草子、徒然草といった中学校の教科書に出てくる単語も掲載されています。
1単語につき。1分程度で読めるボリュームですので、時間に対して得られる生徒ウケ効果は非常に高い1冊です。
新版 竹取物語 現代語訳付き/角川ソフィア文庫
この書籍でも、竹取物語の全文が掲載されいます。
古文全文→現代語訳全文という順番で掲載されており、古文ページの下部には補足が各ページに記載されています。
どちらかと言えば、竹取物語の全文が掲載された教科書に近いです。
ですので、現代語訳も『竹取物語(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典』に比べ、カチッっとしています。
解説のページでは、成立年代や作者、登場人物のモデルとなった実在人物などが考察されています。また、参考文献として、竹取物語に関連・言及する古典の原典が掲載されています。
1冊目というよりも、2冊目以降として「竹取物語をより深く理解したい」方や、訳者による解釈の違いなどを調べたい方向けの書籍です。